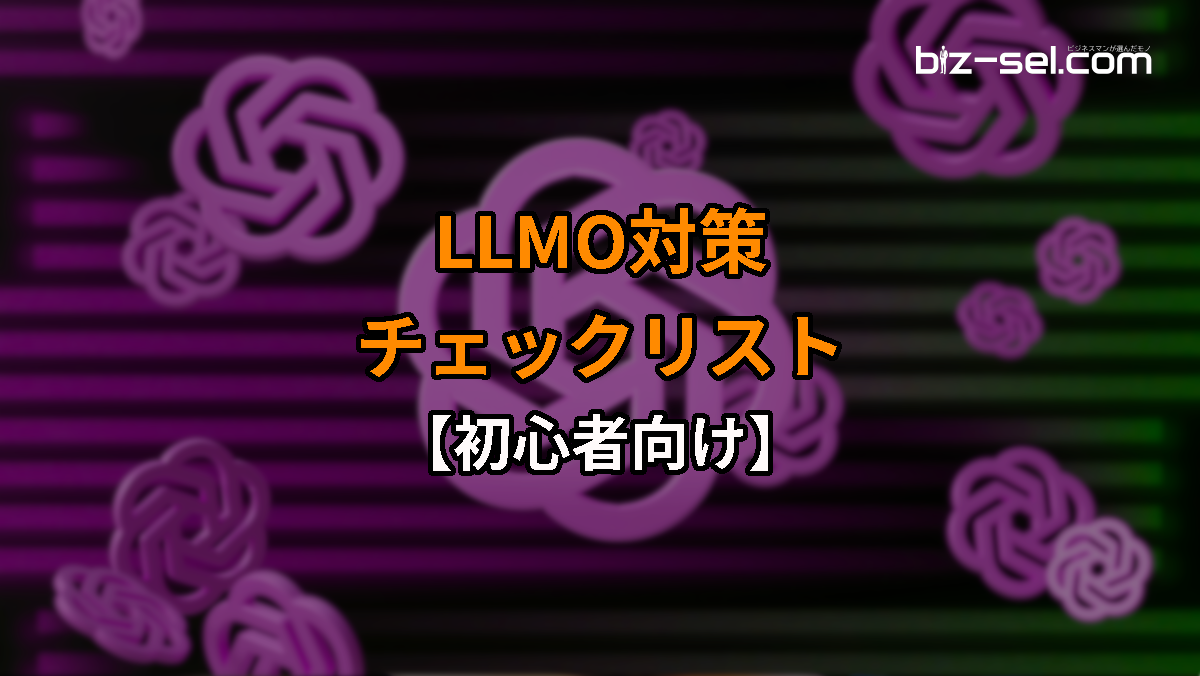LLMOを意識した記事を書くためには何をすればいいんだろう?
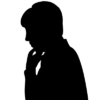
LLMO対策に必要なチェックリストを初心者向けにまとめました。
本記事を読んで、AI時代に対応したLLMO対策を実践しましょう。
今後、AI検索からのアクセスが増えていくことは確実であり、LLMO対策は必要です。
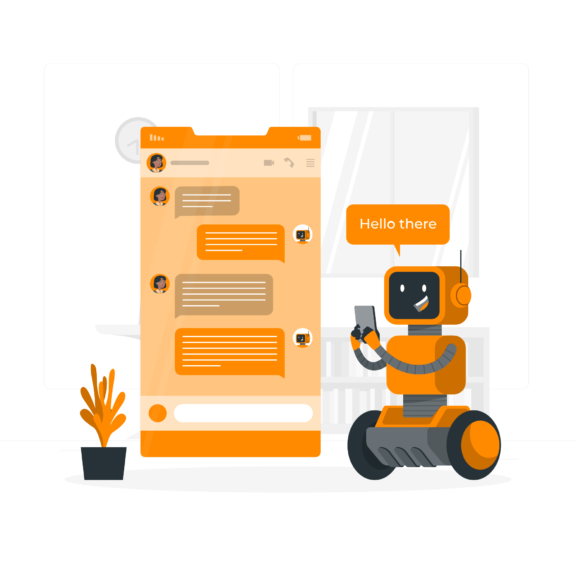
LLMO対策の必要性を理解して、本記事の内容を実践しAI検索の流入数を増やしましょう。
この記事を書いた人
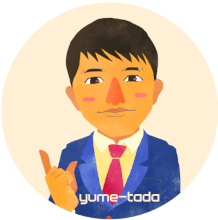
ゆめ ただ
グログ歴 5年目。
普通のビジネスマンとして働きながらFIREを目指す。
独学でゼロからブログを立ち上げる。
Dockerのローカル仮想環境を作りLinux環境も触るように。
4年目でSEO検定1級に合格し地道にスキルアップ。
次はWordPress以外のCMSに手を出そうか悩み中。
気になるところは、直接目次をクリックしてみてみましょう!
1. コンテンツの自然さ・文脈理解
1.1 文章はAIが理解しやすい論理的な流れになっているか
文章全体が論理的で、段落や文の順序が自然であることを確認します。
全体の流れが飛躍したり、前後関係がわかりにくい場合、AIも要点の抽出や理解が困難になります。
はじめに記事の目的や背景を明確にして、具体的な手順や説明を段階的に書くことが重要。
文章の順序を論理的に整理することで、情報がスムーズに伝わり、読み手やAIが理解度が高まります。
まとめ:「まず記事の目的を明確に述べ、次に手順を段階的に説明する。」
1.2 同じ表現やフレーズの繰り返しがなく、自然な文章になっているか
語尾やフレーズの繰り返しが多いと、読者は単調に感じ、AIも冗長情報として認識してしまう場合があります。
文末表現や言い回しを工夫して、多様なバリエーションを用いることが重要。
同義語や言い換えを活用し、文章全体のリズムを整えることで、読みやすくなります。
特に長文の記事では、AIによる要約の精度も上がり、読者の理解スピードも向上します。
実際の例文:「SEO対策は重要。検索順位向上に効果的な方法を順に説明します。」
1.3 段落ごとのテーマが明確で、一文で複数の内容を詰め込んでいないか
段落ごとに伝えたいテーマを明確に設定することで、読者やAIが文章を整理して理解しやすくなります。
文中に複数の情報を詰め込むと、情報の優先度や論理関係が曖昧になり意味の把握が困難に。
テーマを明確にして1つの情報に絞ることで、AIの理解や要約も容易になります。
特に教育系記事や手順書ではこの方法が有効です。
実際の例文:「この段落では、キーワード選定の方法について詳しく解説します。」
1.4 読者の質問に答える形式(Q&Aやステップ形式)を含んでいるか
読者の疑問に直接答える形式を取り入れると、文章の理解が格段に向上します。
Q&Aやステップ形式は、読者の検索意図に応じて情報を整理できるため、AIも要点を抽出しやすくなります。
また、質問を投げかけることで読者からの注意を引き、1問1答で理解度を高めることが可能です。
手順や順序を明確にできるため、解説やマニュアルに有効な構成となります。
実際の例文:「Q: SEOで最初に行うことは何ですか? A: まずキーワードの選定です。」
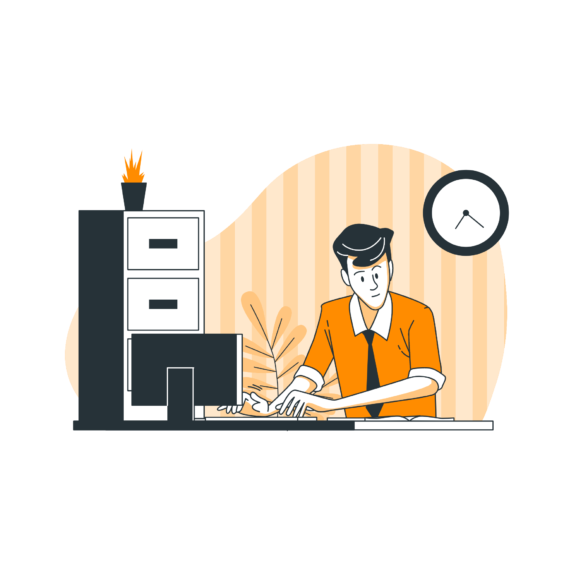
2. 情報の独自性・価値
2.1 独自情報や体験談を盛り込んでいるか
記事の価値を高めるには、情報の再掲やAI生成文だけに頼るのではなく、独自の調査結果や実体験に基づく情報を盛り込むことが重要。
独自情報は読者にとって新鮮で有益であり、信頼性を高める効果があります。
さらに、AIも独自の情報を含む文章を解析する際に、記事の特徴や独自性を正確に理解しやすくなります。
体験談やケーススタディを具体的に示すことで、読者は内容をイメージしやすく、納得度も向上します。
実際の例文:「当サイトの調査では、記事公開後3ヶ月でアクセス数が平均1.5倍になりました。」
2.2 データや統計、図表など具体例を必ず提示しているか
具体的な数値や統計、図表を含めることで、記事の説得力と信頼性が飛躍的に向上します。
AIは文章中の定量情報を効率的に抽出でき、要点整理や要約に役立てることができます。
具体例を挙げることにより、抽象的な説明だけでは伝わりにくい情報を視覚的に理解させることも可能。
統計情報や図表は、読者がデータを比較・分析する際にも役立ち、記事全体の実用性や専門性を高めます。
実際の例:「表1:月間検索数、CPC、競合性の比較」
2.3 他サイトと同じ内容の単なる要約になっていないか
既存記事の内容を単にまとめただけでは、読者に新しい価値を提供できず、AIや検索エンジンの評価も低下する可能性があります。
独自の分析や新しい視点を加えることで、オリジナル性を高め、読者に有益な情報を届けることが可能。
さらに、新しい切り口や具体的な手法を盛り込むことで、専門性や実用性が向上し、AIによる要約や理解もしやすくなります。
実際の例文:「他サイトでは触れられていない、内部リンク最適化の具体的手法を紹介します。」
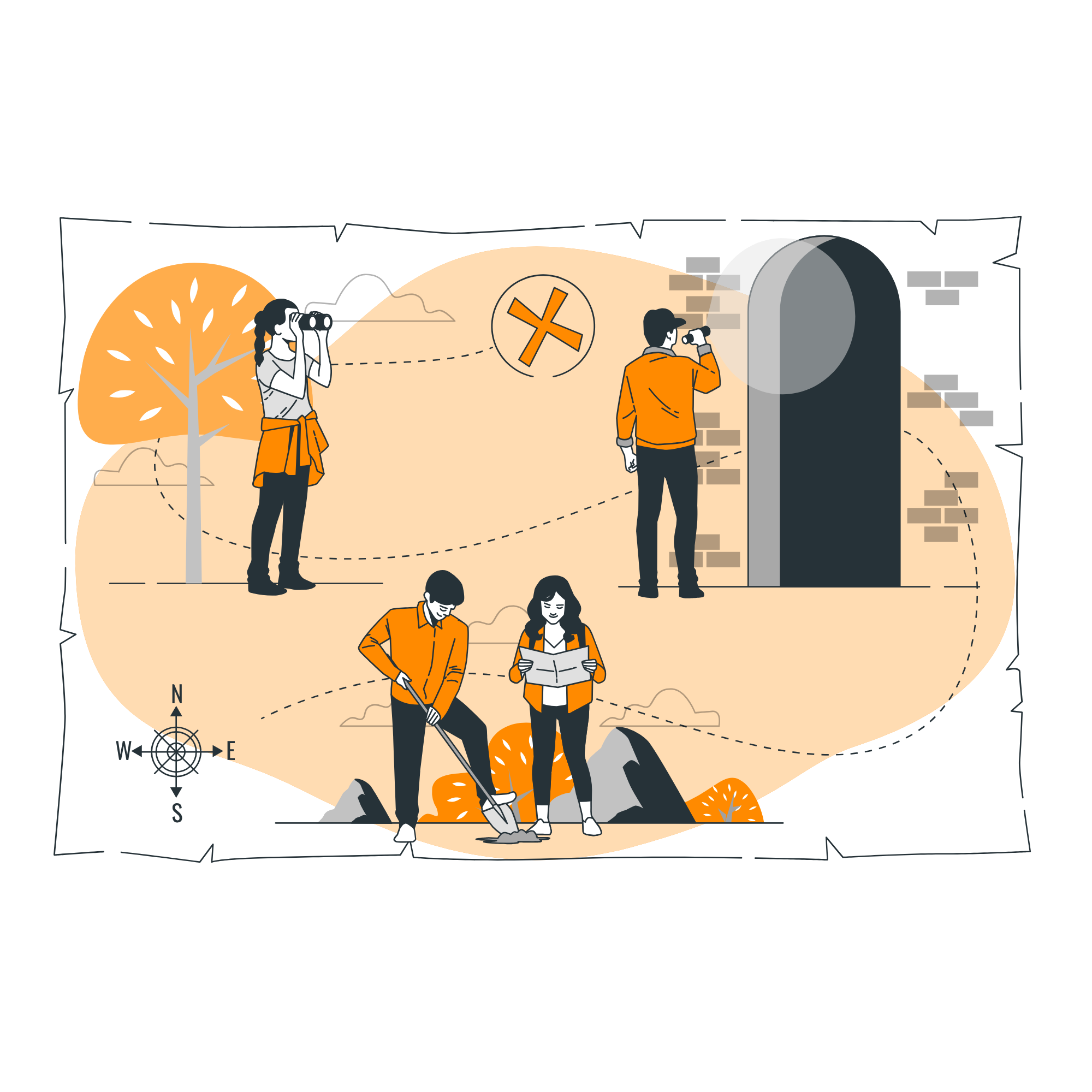
3. 文体・表現の多様性
3.1 語尾や表現のパターンが偏らず自然か
文章が単調にならないよう、語尾や表現のバリエーションを意識することが重要。
文章にリズムや抑揚をつけることで読者の集中力を維持し、AIも文章構造を把握しやすくなります。
特に長文の記事では、同じ語尾やフレーズが繰り返されると理解が困難になり、離脱につながることも。
様々な表現で自然で親しみやすい文章にし、記事全体を読みやすくしましょう。
実際の例文:「SEO対策は重要です。しかし、手順を理解すれば誰でも取り組めます。」
3.2 専門用語は必要に応じて説明や注釈を加えているか
専門用語をそのまま使用すると、初心者や知識が浅い読者には理解が難しくなります。
適切な注釈や簡単な説明を加えることで、AIも用語の意味を文脈から正確に把握可能に。
特にSEOやIT関連の記事では専門用語が多く登場するため、注釈や補足説明は必須です。
読者に負担をかけずに情報を伝える工夫は、記事の信頼性や読了率向上にもつながります。
実際の例文:「CTR(クリック率)とは、広告やリンクがクリックされた割合を示します。」
3.3 読者目線の文章(会話調や問いかけなど)を取り入れているか
読者に直接語りかけるような文章は、記事が親しみやすくなり、理解度の向上にもつながります。
疑問や問いかけ形式を活用することで、読者は自分の興味や課題と照らし合わせながら読むことができます。
記事が単なる情報提供で終わらず、参加型のコンテンツに。
AIもこの形式を解析することで、文章の意図や焦点をより正確に理解できます。
実際の例文:「ここで疑問に思うかもしれません。内部リンクはどのように設計すればよいのでしょうか?」

4. 構造化と可読性
4.1 見出し階層(H2/H3/H4)が論理的で、内容が整理されているか
記事全体の構造を明確にするために、見出しは階層的に整理することが重要。
H2は大きなテーマ、H3はその詳細、H4はさらに具体的な補足という形で構造化することで、情報の優先度や関係性を把握しやすくなります。
また、AIも見出しの階層構造を利用して要点抽出や要約を行えます。
階層構造を意識することで、記事全体が整理され、情報の見落としを防ぎ、読みやすさと理解度が高まります。
実際の例文:「H2:SEO対策の基本、H3:タイトル最適化、H3:内部リンクの活用」
4.2 箇条書きや表を使い、情報を分かりやすく提示しているか
文章だけで情報を伝えると、長文になり視覚的に理解しにくくなることも。
箇条書きや表を活用することで、情報を整理して簡潔に提示でき、短時間で内容を把握しやすくなります。
AIも箇条書きや表の構造を解析することで、重要情報を抽出しやすくなります。
特に比較情報やステップ形式の手順を示す際は、視覚的な整理が有効。
記事の利便性と理解度が大幅に向上します。
実際の例文:「- キーワード選定 - 内部リンク設計 - コンテンツ作成」
実際の例文(表):「表:月間検索数、CPC、競合性の比較一覧」
4.3 記事全体が要約や抽出しやすい構造になっているか
記事全体の要点を理解しやすくするために、段落ごとに結論や重要情報を冒頭に記載することが望ましいです。
文章の構造を意識して情報を整理することで、内容の抽出や要約が容易になります。
また、記事を複数回参照する場合でも、必要な情報をすぐに見つけられるようになり、利便性が向上します。
構造化された記事はSEOの評価にも有効です。
実際の例文:「各段落の冒頭に結論を記載:『内部リンクはSEO効果を高めるために重要です』」
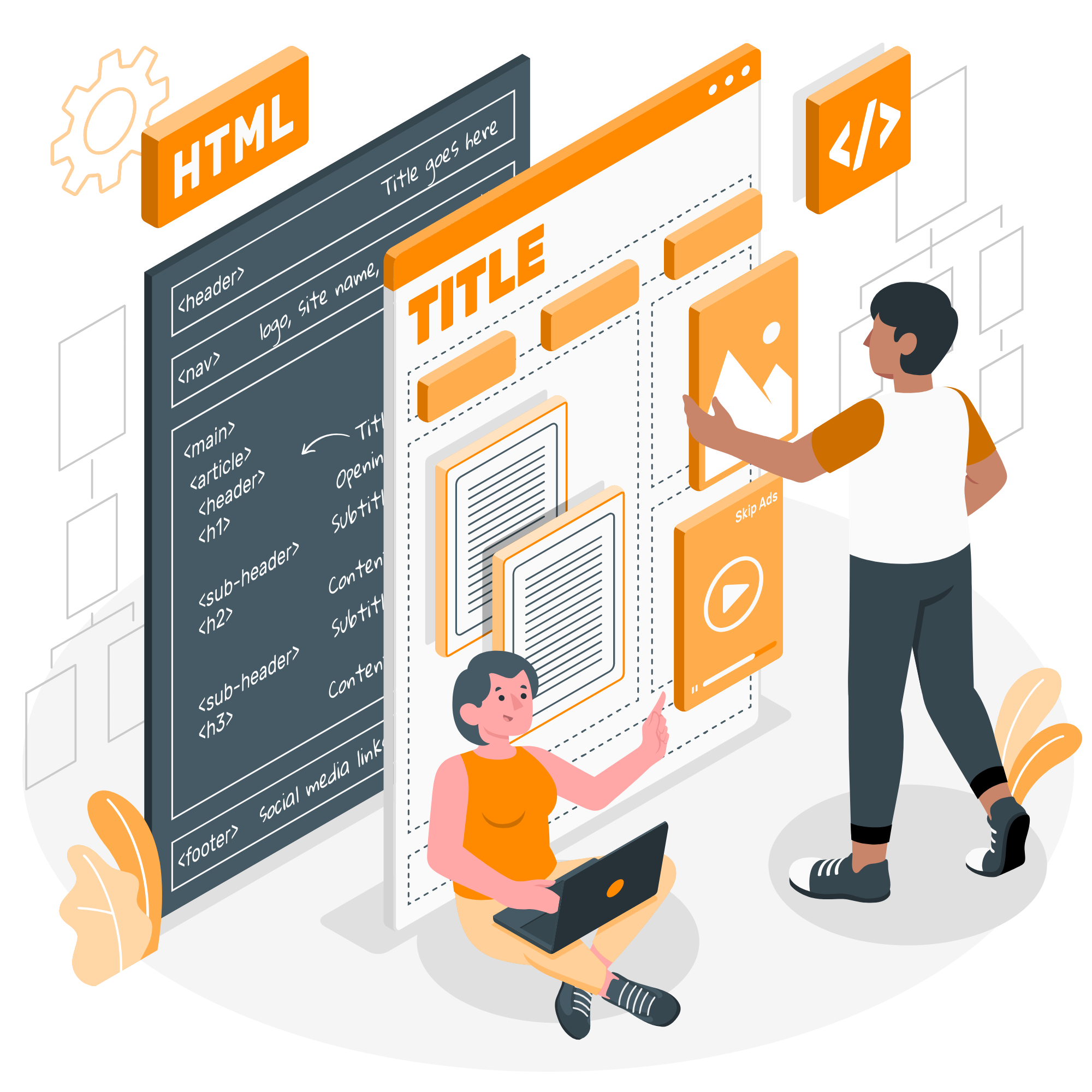
5. 情報の信頼性
5.1 情報源が明確で、必要に応じて引用を提示しているか
記事の信頼性を確保するためには、データや統計、出典を明確に示すことが重要。
情報源を明記することで、読者は内容の正確性を確認でき、AIも引用情報を参照して要点を把握できます。
特に専門的なテーマや数値データを扱う場合は、信頼できる公的機関や公式データを引用しましょう。
出典の明示は記事全体の透明性を高め、読者の納得感と信頼度を向上させます。
実際の例文:「出典:経済産業省『電子商取引市場調査2025』」
5.2 数値や統計は正確かつ最新のデータを使っているか
記事に使用するデータは、古い情報や不正確なデータではなく、最新かつ正確な情報を使用することが重要。
古いデータを用いると読者に誤解を与えたり、記事全体の信頼性を損ねたりする可能性があります。
定期的にデータを更新し、最新の情報を取り入れることで、記事の精度や説得力が向上し、AIによる要約や解析も正確になります。
実際の例文:「2025年の調査では、EC市場の前年比成長率は5%でした。」
5.3 誤解を招く表現や曖昧な断定を避けているか
断定的すぎる表現や曖昧な表現は、読者に誤解を与える場合があります。
特に予測や分析に関する情報では、「〜かもしれません」「〜と考えられます」といった表現を用いて、
確実性を調整しつつ正確な情報提供を心がけましょう。
AIも文章の曖昧な部分を判別しやすくなるため、情報の要約や整理の精度が向上します。
正確かつ客観的な表現を心がけることが重要です。
まとめ:「〜かもしれません、〜と考えられます、といった表現で確実性を調整します。」

6. 更新・改善
6.1 公開後も内容を定期的に見直しているか
記事公開後も、定期的に内容を確認し、古くなった情報やリンクを更新することが重要。
特にSEOや市場動向に関する情報は変化が速いため、定期的な見直しを行うことで、記事の信頼性と正確性を維持できます。
AIも更新情報を学習できるため、古い情報による誤解や誤った要約を防ぐことが可能。
計画的な更新は、読者満足度の向上にもつながります。
実際の例:「半年ごとにSEOデータを確認し、記事内容を更新しています。」
6.2 古くなった情報やリンクは随時更新しているか
リンク切れや古い情報を放置すると、読者に不便を与えるだけでなく、SEOや記事評価にも影響します。
古くなった情報は最新情報に差し替え、正確性を保つことが重要。
また、AIも正確な情報に基づいて要約や解析を行えるため、記事全体の精度が向上します。
定期的なチェック体制を構築しましょう。
実際の例:「リンク切れが確認されたため、公式サイトの最新URLに差し替えました。」
6.3 AIの評価傾向や生成アルゴリズムの変化に応じてリライトしているか
AIの生成アルゴリズムや評価指標は日々進化しています。
このため、記事の構造や表現も最新のAI評価に適合させることが重要。
見出し構造や文章表現を最適化することで、AIによる要約や情報抽出の精度が向上し、理解しやすい記事になります。
アルゴリズム変化に対応したリライトは、記事の長期的価値を維持する手段となります。
実際の例:「最新のAI評価基準に合わせ、見出し構造を再整理しました。」
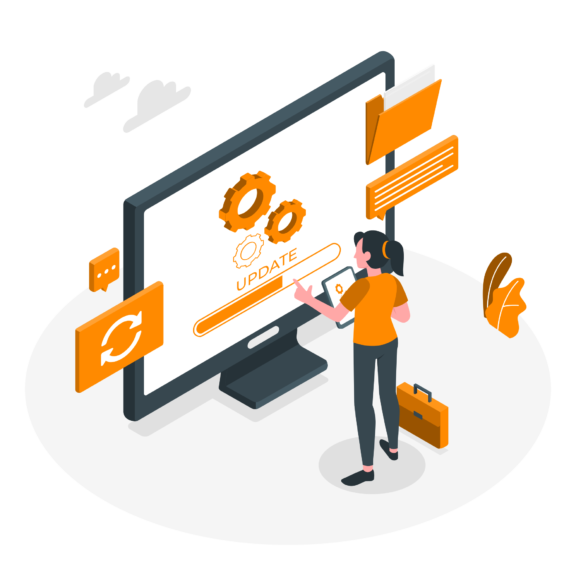
7. 最低限のSEO
7.1 タイトル・見出しに主要キーワードを自然に含めているか
検索エンジンでの可視性を高めるためには、タイトルや見出しに主要キーワードを自然に含めることが重要。
無理に詰め込むと文章が不自然になり、読者の読みやすさも損なわれます。
キーワードは文脈に沿った形で配置し、記事全体の論理的な流れを維持しながら、
検索エンジンと読者に配慮した構成にすることが必要です。
実際の例文:「タイトル:『初心者向けSEO対策ガイド2025』」
7.2 内部リンクや外部リンクを適度に活用しているか
関連ページへの内部リンクや、信頼性の高い外部ページへのリンクを適度に設置することで、記事の情報価値を高められます。
内部リンクはサイト内回遊を促進し、SEO評価にも影響します。
外部リンクは情報源の信頼性を補強し、読者により詳細な情報を提供できます。
AIもリンク構造を解析して情報の関連性や重要性を判断しやすくなります。
実際の例:「本文中に関連ページへの内部リンクを設置:『SEO基礎知識はこちら』」
7.3 モバイル表示での可読性は確保しているか
スマートフォンやタブレットでの閲覧でも読みやすさを確保することは必須。
フォントサイズや段落構成、改行位置、画像サイズを最適化し、縦スクロールでも快適に読めるよう調整しましょう。
モバイルユーザーは増加傾向にあり、SEO評価にも影響します。
読者の満足度が高められ、AIによる解析や要約も適切に行えるようになります。
実際の例:「スマホ表示での改行や見出しサイズを調整し、縦スクロールでも読みやすくしました。」

8. クローラビリティ
8.1 llms.txtがルート直下に設置されているか
LLMS.txtは検索エンジンやAIクローラーがサイトの構造や重要ページを認識するための指標ファイルです。
ルート直下に設置されていない場合、クローラーが正しくアクセスできず、サイト全体の解析や要点抽出が不完全になる可能性があります。
正しく設置することで、AIはサイトのページ構造や優先度を効率的に把握でき、SEO評価や情報抽出の精度が向上します。
実際の例:「https://example.com/llms.txt をルート直下に設置しています。」
8.2 GPTBotのクロールを許可しているか
GPTBotなどのAIクローラーを許可することで、サイトの最新情報やコンテンツ構造を効率的に解析してもらえます。
クロールを制限すると、AIによる要約や解析、検索結果への反映が遅れたり不完全になる可能性も。
適切なアクセス許可を設定することで、AIは正確にサイト情報を収集し、ユーザーに提供する情報の質を高めることが可能です。
実際の例:「robots.txtでGPTBotのクロールを許可し、最新ページ情報を取得可能にしています。」
robots.txt ファイル
User-agent: gptbot
Disallow: /
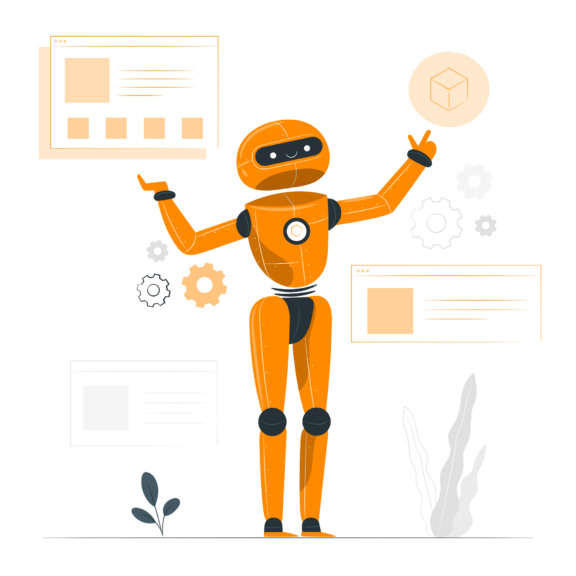
9. LLMO対策チェックリスト表【まとめ】
| 大項目 | チェック項目名 | 実際の例 |
|---|---|---|
| 1.コンテンツの自然さ・文脈理解 | 文章はAIが理解しやすい論理的な流れになっているか | 「まず記事の目的を明確に述べ、次に手順を段階的に説明します。」 |
| 同じ表現やフレーズの繰り返しがなく、自然な文章になっているか | 「SEO対策は重要です。検索順位向上に効果的な方法を順に説明します。」 | |
| 段落ごとのテーマが明確で、一文で複数の内容を詰め込んでいないか | 「この段落では、キーワード選定の方法について詳しく解説します。」 | |
| 読者の質問に答える形式(Q&Aやステップ形式)を含んでいるか | 「Q: SEOで最初に行うことは何ですか? A: まずキーワードの選定です。」 | |
| 2. 情報の独自性・価値 | 独自情報や体験談を盛り込んでいるか | 「当社の調査では、記事公開後3ヶ月でアクセス数が平均1.5倍になりました。」 |
| データや統計、図表など具体例を必ず提示しているか | 「表1:月間検索数、CPC、競合性の比較」 | |
| 他サイトと同じ内容の単なる要約になっていないか | 「他社の記事では触れられていない、内部リンク最適化の具体的手法を紹介します。」 | |
| 3. 文体・表現の多様性 | 語尾や表現のパターンが偏らず自然か | 「SEO対策は重要です。しかし、手順を理解すれば誰でも取り組めます。」 |
| 専門用語は必要に応じて説明や注釈を加えているか | 「CTR(クリック率)とは、広告やリンクがクリックされた割合を示します。」 | |
| 読者目線の文章(会話調や問いかけなど)を取り入れているか | 「ここで疑問に思うかもしれません。内部リンクはどのように設計すればよいのでしょうか?」 | |
| 4. 構造化と可読性 | 見出し階層(H2/H3/H4)が論理的で、内容が整理されているか | 「H2:SEO対策の基本、H3:タイトル最適化、H3:内部リンクの活用」 |
| 箇条書きや表を使い、情報を分かりやすく提示しているか | 「- キーワード選定 - 内部リンク設計 - コンテンツ作成」 | |
| 記事全体が要約や抽出しやすい構造になっているか | 「各段落の冒頭に結論を記載:『内部リンクはSEO効果を高めるために重要です』」 | |
| 5. 情報の信頼性 | 情報源が明確で、必要に応じて引用を提示しているか | 「出典:経済産業省『電子商取引市場調査2025』」 |
| 数値や統計は正確かつ最新のデータを使っているか | 「2025年の調査では、EC市場の前年比成長率は5%でした。」 | |
| 誤解を招く表現や曖昧な断定を避けているか | 「〜かもしれません、〜と考えられます、といった表現で確実性を調整します。」 | |
| 6. 更新・改善 | 公開後も内容を定期的に見直しているか | 「半年ごとにSEOデータを確認し、記事内容を更新しています。」 |
| 古くなった情報やリンクは随時更新しているか | 「リンク切れが確認されたため、公式サイトの最新URLに差し替えました。」 | |
| AIの評価傾向や生成アルゴリズムの変化に応じてリライトしているか | 「最新のAI評価基準に合わせ、見出し構造を再整理しました。」 | |
| 7. 最低限のSEO | タイトル・見出しに主要キーワードを自然に含めているか | 「タイトル:『初心者向けSEO対策ガイド2025』」 |
| 内部リンクや外部リンクを適度に活用しているか | 「本文中に関連ページへの内部リンクを設置:『SEO基礎知識はこちら』」 | |
| モバイル表示での可読性は確保しているか | 「スマホ表示での改行や見出しサイズを調整し、縦スクロールでも読みやすくしました。」 | |
| 8.クローラビリティ | llms.txtがルート直下に設置されているか | 「https://example.com/llms.txt をルート直下に設置しています。」 |
| GPTBotのクロールを許可しているか | "「robots.txtでGPTBotのクロールを許可し、最新ページ情報を取得可能にしています。」 User-agent: gptbot Disallow: /" |
あなたも、LLMO対策チェックリストをもとに、記事の見直しをしてみましょう。